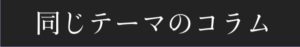アメリカ・アラバマ州に住む13歳の少年が、交通事故で脳死と判定された。
親が臓器提供の書類にサインした翌日、少年は意識を取り戻したという。
それから一ヶ月あまり、少年は頭の傷が痛々しいまま、BBCの取材に応じて、普通に受け答えをしている。
歩行は母親の介助が必要なようだが、ラジコンカーの操作をしている様子からは、手足も動くようだ。
「脳死になると、二度と目覚めることはない」
「生命維持装置を外せば、呼吸は停止する」
そのように医師から言われたら、苦しみを長引かせたくないと家族が思うのは当然だ。
患者が子供なら、生きていた証を残したい、誰かの命を繋いであげたい、と願う心情を、誰も責めたりすることはできない。
ただし、このアラバマ州の少年のようなことは、起こり得るのだ。
日本の臓器移植法改正が国会で議論されていた2009年当時、私は沖縄県立中部病院で、二ヶ月間にわたって密着取材をしていた。
NICUの責任者を務める小児科医・小濱守安が、深夜の病院でこんなことを話してくれた。
「脳波がフラットになった子供が、しばらくして活動を再開した経験がある。
だから、脳波がフラットだから、反応がないからというだけで、僕は人工呼吸器を外すのは、すごく抵抗がある。
この子の体を、他の子のために、ということは言えない」
現在、日本の脳死判定は、「深い昏睡」、「瞳孔の散大と固定」、「脳幹反射の消失」、「平坦脳波」、「自発呼吸の停止」の5項目の検査を行う。
さらに、6時間以上開けて、再び同じ検査を行って、「脳死」が確定する。
6歳以下の子供は、脳にダメージを受けても回復する力が高いため、2度目の検査は24時間以上空ける。
かつて日本では、15歳以下はドナーになれなかったので、多額の募金を集めて欧米で臓器移植を受ける子供たちが相次いだ。
これに対する海外からの批判もあり、2010年に法改正された。
日本臓器移植ネットワークは、ホームページで次のように訴える。
「アメリカでは「脳死は人の死」とされているため、ほとんどが脳死後の臓器提供で、年間8,000~9,000人もの臓器提供者がいます。
2015年、日本の提供数315件に対し、アメリカは79.3倍の24,980件でした」
だからといって、我が子が脳死と診断された時に、臓器提供を検討すべきとするのには賛成できない。
日米のドナー数の違いは、宗教的な背景と、医療制度(費用)の違いが大きく影響しているからだ。
アメリカの医療費が桁違いに高いことは周知の事実で、ICU(集中治療室)に1週間入院で約1千万円かかったケースを聞いた。
延命治療や蘇生治療は、経済力がないとできないのだ。
日本で、脳死臓器移植を推進すべき、と考えている人々の決まり文句がある。
〝日本は今でも臓器提供の数が少ない。脳死臓器移植の後進国だ〟
冷静に考えてみると、先天性の病などで臓器移植が必要な子供の数と、事故などで脳死になる子供の数に相関性を見出すことはできない。
そもそも、必要とされる臓器の〝需要と供給のバランス〟が均衡することなど、幻想なのだ。
これを可能にできるのは、カズオ・イシグロが書いた「私を離さないで」の世界だけだろう。
イシグロは、医療の進化がもたらした残酷性と矛盾を表現したかったのかもしれない。