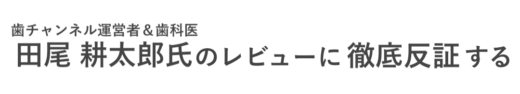
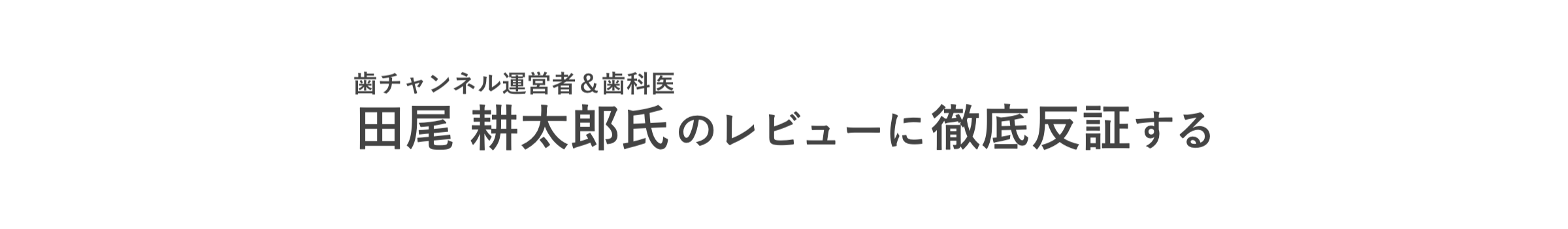
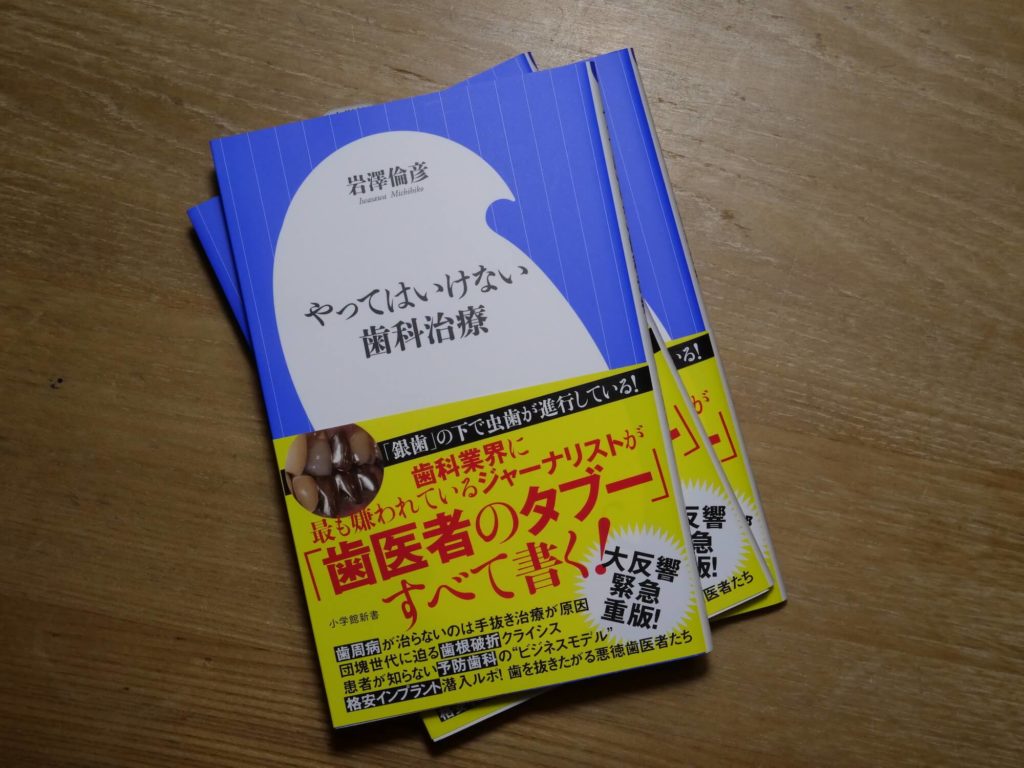
無責任な1回目のレビュー
新刊本を出版すると、取材先やメディア関係者に、お礼と本の紹介のお願いを兼ねて、「献本」するのが慣例だ。
今年5月30日に発刊となった、拙著「やってはいけない歯科治療」(※以下、本書)は、取材にご協力して下さった歯科関係者、新聞社、雑誌、テレビ、ウェブメディアの関係者に、版元の小学館編集部から送らせていただいた。
献本先に選んだ一人が、歯科医で実業家の田尾耕太郎氏である。彼が運営する「歯チャンネル88」は、患者の治療相談にボランティアの歯科医が無料で回答する、知る人ぞ知る、歯科専門サイト。
田尾氏は、このサイトで患者と歯科医の注目を集め、歯科医院のHP制作や管理、SEO対策などの事業を手がける。歯科ネット分野では、オピニオンリーダー的な存在でもあり、今年3月には、短時間だが、大阪市内で直接お会いした。
6月23日、田尾氏はアマゾンのカスタマーレビューと自身のFacebookに、1回目の本書レビューを投稿した。
献本お礼。
早速読ませて頂きましたが、良い点は格安インプラントの無料相談に潜入調査までされているなど、かなり力を入れて取材をされていること。また、データも極力信頼性が高いものを探そうと努力されているのが伝わってきました。
悪かった点は、書かれている内容の7割くらいは正しいのですが、3割ほどは医学的に完全に誤っているところです。これは取材協力をしている歯科医師の人選の問題が大きいのではないかと思いました。(専門的な内容に関しては一応歯科医師に取材をしているのですが、そもそもその歯科医師が間違えている。というより、そういった歯科医師をあえて選んでいるのではないか?と思われる節がある)
最大の問題は、そういった医学的に誤った情報を根拠に、日本の歯科界への問題提起を行ってしまっているところです。本書に社会的意義があるとすれば歯科界への問題提起だと思いますので、それならば医学的な情報部分についてはもっと第三者の歯科医師に意見を求めるなりして、突き詰めて頂くべきだったかと思います。(本書の意義が患者さんへの情報提供だとすれば、重要な部分での医学的誤りが致命的なのでこの本は30点です)
岩澤さんは「歯科業界に最も嫌われているジャーナリスト」を自負されていますが、僕は問題提起はどんどん行って頂きたいと思っています。
ただ、今回のように中途半端な状態ではただ歯科への不信感を煽るだけで、真に問題提起とは言えません。そこが歯科業界に嫌われている最大の理由なのではないかなぁと。
本書の内容に関して問題部分を指摘し、その根拠を提示させて頂こうかとも思ったのですが、間違いを指摘してその根拠となるデータをまとめていくという作業は、間違えた情報を元に記事を書く何倍もの労力を必要とします。
なので、きちんとお仕事として依頼を受けるという形でなければ、正しい情報を発信していくということに並々ならぬこだわりを持っている僕ですら正直気が進みません。ですが、次回作はぜひこの問題点を解消して、より良い情報発信をして頂けることを期待しています。
問題点が気になりすぎたのでそこばかり書いてしまいましたが、7割くらいは本当のことが書かれていると思いますし、口コミサイトや某予約システムなど僕も大きな問題だと感じていることに対する指摘もあります。網羅的にではなくこうしたいくつかの問題に焦点を絞って掘り下げていくという形だと、比較的簡単により質の高い問題提起が出来るのではないかと個人的には思いました。
(田尾 耕太郎氏 6月23日アマゾン・カスタマーレビューより原文まま転載)
本書は、歯科業界が隠してきたタブーを徹底的に明らかにして、患者が自分自身の治療を深く知るべき、という問題提起をしている。
そのため、歯科関係者にとっては知られたくない〝不都合な真実〟も遠慮なく書いた。これは、歯科業界と何にもしがらみがない、私のようなジャーナリストにしかできない役割だと思っている。
これまで散々歯科治療に苦労してきた患者たちが知りたいのは、歯科医の本音であり、普段は見ることができない治療現場の裏側なのだ。
当然のことながら、歯科関係者から反発が起きることは予想していたし、むしろ反応がなければ、この本を書いた意味がないとさえ考えていた。
しかし、田尾氏の1回目の投稿は、肩透かしを食らったような失望感しかなかった。
「3割は医学的に完全に間違っている」とまで言いながら、何も根拠を示していなかったからだ。そこまで批判するなら、しっかりと説明を果たすのが最低限の責任である。これでは、本書に対する信用棄損でしかない。
さらに、長い臨床経験を持ち、第一線の研究者でもある歯科医の方々に対して、「人選の問題」と揶揄するのは、社会人としての礼節を欠いた言説だ。
そして、本書では、多くの患者たちが独善的な歯科医の治療によって翻弄され、身体的、精神的、経済的に大きな被害を受けていることを、繰り返し描いた。だが、田尾氏のレビューは、患者たちについて何も言及していない。
結局、田尾氏の投稿目的は、自分のクライアントである特定の歯科医に向けたパフォーマンスなのではないか。この投稿後、田尾氏からは直接メッセージが届いたので、レビューに対する私が感じた思いは伝えた。
「老境」歯科医の真意とは
36年の臨床経験を持つ一人の歯科医が、私の事務所あてにメールをくれた。田尾氏が、1回目のレビューを投稿する、前日(6月22日)である。
お付き合いがない方だったが、本書の学問的な誤りなどについて、具体的に指摘され、何らかのかたちで訂正したほうがよいのでは、と結んであった。
これを受けて、アドバイザーの歯科医、担当編集者と協議を行った結果、学問的な誤記と、誤解を招く可能性がある記述が5箇所あると判断した。
6月27日、私の事務所HPに、読者と関係者に対するお詫びと、修正内容について掲載、連絡を下さった歯科医に報告した。
そのベテラン歯科医は、アマゾンの本書レビューに「老境」という名で投稿されて、一連の経緯を記している。
「老境」歯科医は、ご自身の名前や歯科医院を明かしていない。純粋に患者のためにどのような情報提供が必要か、という意識から行動されたのだと思う。
〝アマゾンに投下〟投票を歯科医に催促した2回目のレビュー
本書に対する田尾氏の1回目のレビューは、アマゾンの利用者にそれほど注目されなかったらしい。「役に立った」のボタンを押したのは僅かだったので、いくつかあるレビューの中に埋もれていた。
私から仕事として依頼したわけではないが、田尾氏は自身のFacebookで本書に対する2回目のレビューを〝投下〟したと宣言した。
「老境」歯科医からの連絡を受け、私が修正箇所を公表してから10日後のことである。
「やってはいけない歯科治療(小学館新書)」の レビュー&問題があると思われる記載内容部分についての指摘を、Amazonに投下しておきました。
Amazonのレビューは「参考になった」が押された数が多いものが優先的に表示されやすくなるようなので、よろしければご協力のほどよろしくお願いいたします。
(田尾 耕太郎氏 7月6日 Facebook投稿より 原文まま転載)
アマゾンのレビュー投稿を「投下」と表現したり、表示順位を上げるために投票を催促するなど、いかにもネット関連の業者らしい振る舞いだ。
田尾氏の目論見通り、投稿から2日間で100人以上が協力した結果、本書のアマゾン・カスタマーレビューのトップに田尾氏のレビューが表示された。
協力したFacebookのお友達のことを、田尾氏は「共犯者」と呼んでいる。その大半が、歯科医であり、彼が運営する無料治療相談サイト「歯チャンネル」の常連回答者の顔ぶれも交じっている。
2回目のレビューは、実に約4900文字の大作だ。この無駄に長いレビューを読んだ上で協力しているなら、お友達の歯科医たちも「共犯者」としての自覚をお持ちなのだろう。
そこで「3割ほどは医学的に完全に間違っている」と田尾氏が主張するレビューについて、項目ごとに整理番号をつけてみると、全34項目に及んでいた。
アドバイザーの歯科医と共に検証作業に入ると、すぐに牽強付会という言葉が思い浮かんだ。脈略を無視した文章の引用、不自然な解釈、引用論文やガイドラインの主旨と整合性がない、中には指摘や認識自体が「間違っている」ものさえある。
「3割は医学的に完全に間違い」というレビューの目的は、本書の信用毀損なのだろう。私としては、取材に協力して下さった方々の名誉のためにも、このような一方的な指摘を、受け入れることはできない。
検証結果を5つに分類すると、次のようになった。
【全指摘34項目】
- 詭弁というべき指摘 →16
- 見解の相違 →9
- 本書の内容に同意 → 4
- 修正済みの指摘 → 3
- 指摘自体が誤り → 2
〝お友達チェック〟の狙い
田尾氏は、7月6日に投稿した2回目のアマゾン・レビュー冒頭で、わざわざ次の前置きをしている。
「やってはいけない歯科治療」の詳細レビュー&問題があると思われる記載内容部分についての指摘です。
当コメントは事前にFacobook上で公開して、妥当な内容になっているかどうか第三者によるチェックをして頂いた上で投稿をさせて頂いています。」
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1850958431650082&id=100002078290107
(※アマゾンカスタマーレビューより誤記のまま原文抜粋、URLの記載は7/6投稿時)
田尾氏が、この前置きをしている理由は「イメージ形成」だろう。
医学論文の場合は、正確性、妥当性について、その分野で実績を上げた研究者などによる査読(評価)を行い、一定の質と信頼性を担保している。Facebookのお友達・歯科医のチェックを受けた、と前置きすることで、レビューが妥当であるかのようなイメージを読者に与えているつもりらしい。
しかし、お友達チェックは、査読とは全く別モノ。正確性や妥当性を、何ら保証するものではない。
さらに田尾氏は、2回目のレビューを投稿した際、自分が運営する「歯チャンネル」と「シカシル」というサイトなどのURLを貼っていたが、医学的な根拠を示すなら、ガイドラインや原著論文を示すのが、常識的な対応である。
歯科医の資格を持つ田尾氏が、こうした流儀を知らないはずがない。
アマゾンでは、投稿者がレビューに便乗して、自社サイトの宣伝などを行うことを禁じている。おそらくこれが理由で、アマゾンのレビューからは、6日付けの田尾氏の投稿は消された。
8日付でレビューは、再投稿されていたが、田尾氏は自社サイトのURLをカットしている。
それでは、田尾氏のレビューについて項目ごとに、反証していく。
1
<指摘>
p18~57 第一章「銀歯のタブー」
※全体を通してレジンを勧める歯科医師は良心的、銀歯を勧める歯科医師は注意が必要という論調であり、レジンを過大評価、銀歯を過小評価しすぎている傾向がある。
<反証> 詭弁というべき指摘 ①
日本の歯科治療の基本的な方向性を示す「う蝕治療ガイドライン2版」P4の『う蝕治療の現状と問題点』では、次のように述べている。
「旧来の“Drill and Fill” 中心のう蝕治療法からの脱却と、MI(ミニマル・インターベンション)の理念を基本としたう蝕治療法の普及が必須である」
本書は、同ガイドラインの考え方に基づき、前者を象徴するものが、銀歯(金銀パラジウム合金)治療であり、後者がコンポジット・レジン治療であるという解釈を、田上順次・東京医科歯科大副学長、久保至誠・長崎大准教授のコメントを合わせて解説している。
また、レジンよりも銀歯の方が、より歯質を大きく削る必要性が出て、歯を失う連鎖が起きやすい傾向がある。
「レジンを過大評価、銀歯を過小評価」と主張するならば、本書ではなく、「う蝕治療ガイドライン2版」及び、日本歯科保存学会に異議申し立てすべきだろう。
2
<指摘>
p23「森田教授のインレー、クラウンの平均使用年数」
※これは「ダメになった」インレー、クラウンのみを対象としたデータであり、問題なく機能しているインレーやクラウンは含まれていない。
<反証> 詭弁というべき指摘 ②
本書では、平均使用年数について「再治療になった銀歯」=ダメになった銀歯であることを明記して、「数十年経過」する銀歯もあることを示している。
「森田学教授のチームが再治療となった、約3000本の歯を対象に平均使用年数を調査したところ、次のような結果が出た。(中略)」P23
「中には銀歯を入れてから、数十年経過しても何もトラブルがない、という患者もいる」P25
したがって、「問題なく機能しているインレーやクラウンは含まれていない」という指摘をする意味が不明である。
3
<指摘>
p27「通常、歯と修復金属のつなぎ目は、20ミクロン以下が基本とされている。それ以上、隙間が空いていると、ミュータンス菌が侵入して虫歯が再発してしまう。
※ミュータンス菌の大きさは1ミクロン。20ミクロン以下の隙間であっても細菌は侵入するが、細菌の侵入=虫歯の再発とはならない。」
<反証> 見解の相違 ①
ミュータンス菌は、1ミクロンという単独のサイズではなく、バイオフィルム(もしくはプラーク)を形成して歯に付着している。歯と修復金属の隙間が空いているほど、プラークが付着しやすくなり、虫歯のリスクが高まるのは必然である。
「細菌の侵入=虫歯の再発とはならない」と田尾氏は主張するが、銀歯の下に入り込んだ、ミュータンス菌(バイオフィルム)を除去するのは、極めて困難であり、う蝕となる可能性は高いだろう。
4
<指摘>
p30「実は、利益が大きい「セラミック」だけを患者に勧めて、安くて時間のかかる「レジン」という選択肢を提示しない歯医者も多い。」
※セラミックはレジンよりも長持ちし、二次う蝕の発生率も低いというデータが出てきている。利益が大きいからセラミックを勧める歯科医師が多いというのは暴論。レジンはテクニカルセンシティブな材料であり、統計上はセラミックや金属インレーよりも寿命が短く、二次う蝕の発生率も高い。ただし、レジンには歯を削る量が少ないなどの利点もあり、どの材料が適しているのかはケースバイケースである。
https://shikashiru.com/post/48.html
https://minds.jcqhc.or.jp/n/cq/D0003330
<反証> 詭弁というべき指摘 ③
この場面は、保険診療を中心に行う歯科医が、実際に体験した場面を再現している。
患者が白い材料での治療を希望した場合、「利益が大きいセラミックだけを患者に勧めて、安くて時間のかかるレジンという選択肢を提示しない」。
このようなことが、診療現場で頻繁に起きている。
これは、歯科医と患者の双方から証言を得ており、これを「暴論」と決めつけるのは、現実を知らないからではないか。
また、田尾氏は「セラミックはレジンよりも長持ちし、二次う蝕の発生率も低いというデータが出てきている」と述べている。
この論理では「長持ちし、二次う蝕の発生率も低い」なら、歯医者は高額なセラミックだけを提示してもよい、という解釈になるだろう。
これこそが、歯科医の独善性を表していると言える。
「耐久性」「二次う蝕の発生率」「費用」。この3つのうち、どれを最優先にするのか。
最終的に決定するのは、歯医者ではなく、患者であるべきだろう。
「レジンはテクニカルセンシティブな材料であり、統計上はセラミックや金属インレーよりも寿命が短く〜」と田尾氏は主張するが、それは間違いだ。彼自身が引用している「う蝕治療ガイドライン第2版」では、次のように記されている。
「臼歯咬合面(1級窩洞)に対するコンポジットレジン修復とメタルインレー修復の臨床成績に有意な差はない」P139
このように科学的根拠に基づくガイドラインには、レジンと金属(メタル)インレーに統計学的な違いはないと明記されている。したがって、「(レジンは)統計上はセラミックや金属インレーよりも寿命が短く」とする田尾氏の主張は、明らかな間違いだろう。
また、このパートで、田尾氏が貼り付けた2つのリンクのうち、「後者=日本医療評価機構」のみか、「う蝕治療ガイドライン2版」のリンクを提示すれば十分に足りるはずだ。それを田尾氏が運営するサイトのリンクを貼っていたのは、レビューに便乗して自社の宣伝行為とみられても仕方がないだろう。

5
<指摘>
p33「この歯肉圧排をやらないと、「不適合」なクラウンになってしまいます。」
※縁上マージンの場合は圧排不要。また、印象精度については、歯の削り方や、初期治療で歯肉の炎症が無くなっているということも重要。(歯肉の腫れや出血があると、印象を精確に採ることが難しくなる)
<反証> 詭弁というべき指摘 ④
「歯肉圧排」は、歯肉の縁下にマージン(辺縁)が設定されている場合の作業である。そこにわざわざ、「縁上マージンの場合は圧排不要」(※縁上マージン=歯肉より上に辺縁を設定)という説明を加えることは、蛇足でしかない。
このパートでは、銀歯のクラウンで、どのような〝手抜き〟があるのか、イラストを使用して解説しているので、歯科技工について知らない読者でも一目瞭然だと思われる。
また、田尾氏は、印象精度などについて自論を述べているが、これは専門書ではないので、網羅的に記述する必要性はないと判断している。
6
<指摘>
p33「歯型は丁寧に作業すると30分間程度は必要だが、「歯肉圧排」などを省略すれば10分もかからない。」
※確かに丁寧に作業するとそれくらいかかると思うが、そこまでしている歯科医師はごく一部。それも多くが保険外。保険でコンスタントに形成に30分かけるというのは現実的に考えて普通は無理がある。圧排の有無は時間とはそれほど関係が無いように思う。
<反証> 見解の相違 ②
歯科医の習熟度や誠実性によって、チェアタイム(治療にかける時間)は異なる。
見解の相違、というべきものを「問題」として取り上げるのは、いかがなものか。
7
<指摘>
p40「日本の一般大衆が、正しい歯科治療を受けられる日は永久にこない、ということを意味します。」
※技術のチェック制度が無いから、ということのようだが、全く根拠が無い極論であり、一般向けに情報発信を行う媒体としては抜粋が不適当かと思われる。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑤
この記述は、1978年当時、総山孝雄・東京医科歯科大学教授(故人)がスウェーデンを丹念に視察した上で、シンポジウムの場で述べている言葉である。
現在の保険診療は、診療報酬の請求点数だけがチェックされ「治療の質」は問われていない。これが、様々な手抜きや不正請求の温床となっている。
40年前に、総山先生が提言されていた言葉にこそ学ぶべきであり、「抜粋が不適当」という指摘は的外れだろう。
8
<指摘>
p43「患者にとっては「歯を削る量が少なく、その日のうちに治療が終わるレジン」の方がメリットが大きいが、歯医者にとっては「製作を下請けの技工士に任せ、患者には後日、再度来院させる銀歯」の方が効率がいい。」
※レジンが常に患者にとってメリットが大きいとは言えない。患者さんの噛み合わせ等の状況や、歯科医師の知識・テクニックによって、最適な方法は変わる。
<反証> 見解の相違 ③
患者にとってのメリットは何か、判断するのは歯科医ではなく、当事者の患者だ。
ここで述べているのは、レジンと銀歯の相対的なパターンであり、最適な治療法は状況によって異なるのは言うまでもない。見解の相違、というべき指摘だ。
9
<指摘>
p46~56 金属アレルギーに関する記事。ここは良くまとまっていると思う。
本書の内容に同意 ①
10
<指摘>
p60~89 第二章「虫歯治療7つの間違い」
※一章と同じく、全体を通してレジンを過大評価、銀歯を過小評価しすぎている傾向がある。二章は医学的に誤った内容が目立つ。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑥
先の反証1を参照していただきたい。
11
<指摘>
p62「歯ブラシを使うだけでは、プラックは25%しか取り除かれません。 残りの75%はデンタルフロスを使わないと取れないのです。」
※歯ブラシだけでも約60%はプラークを除去できる。また、デンタルフロスを使ったとしても、除去率は100%にはならない(約80%)が、虫歯や歯周病予防のためにプラーク除去率を100%にする必要性はない。歯ブラシだけで十分にプラークコントロール出来ている人もいる。奥歯はデンタルフロスよりも歯間ブラシが有効な場合が多い。(奥歯の隣接面には凹みがあるため)
https://www.club-sunstar.jp/article/lifestyle/brushing/555/
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑦
この部分は、1980年に川村泰雄先生が出版された書籍からの引用である。読者は、当時の知見として、受け止めるのが自然だろう。
ここで示しているのは、最近注目されている「予防歯科」は、40年近く前から川村先生らが提唱していた点である。その声を黙殺しながら、今頃になって注目している歯科業界の無責任な姿勢こそ、猛省すべきだろう。
また、本書のP82では「歯ブラシだけでは口腔内のプラークを6割程度しか除去できない」と紹介しているので、全体を通して読んでもらえば、誤解は生じないだろう。
田尾氏が自身の主張の根拠として示しているURLは、歯ブラシメーカーのサイトだったが、このような場合は学術論文を示すべきである。
12
<指摘>
p64「初期虫歯は、自然治癒する。削らずに見守る方がよい」
※これは非常に誤解を与えやすい表現なので注意が必要。確かに初期虫歯をすぐに削るというのは現在では否定されているが、かといって何もしないというわけではなく、進行していないかどうかの経過観察やブラッシング指導、食事指導、フッ化物使用について指導等が必要である。これらを受け入れてもらえない(もらえそうにない)患者さんに対しては早期治療も選択肢となる。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑧
本書P89のまとめには「初期虫歯は削らない フッ素の塗布はOK」と注意を促している。なにもしなくていい、と述べてはいない。
「口腔ケアや食事指導などを受け入れてもらえそうにない患者」の場合、歯を削る治療が選択肢になるという考え方は、あまりに独善的で問題がある。
勝手に決めつける前に、口腔ケアなどの指導スキルを、まず歯科医が身につけるべきだろう。
13
<指摘>
p73治療にかかる時間は、銀歯の方が圧倒的に短いから、歯医者にとってのレジン修復は、コストパフォーマンスが悪い。
※適当にやればレジンの方が圧倒的に早い(チェアータイムも1回で済む) 。レジンか銀歯か?という材質的な問題よりも、基本に忠実に丁寧に治療されているかどうかが問題。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑨
田尾氏はFBでお友達の歯科医に対して、以下のコメントを返していた。
「金儲けだけ考えるなら、レジンの鼻くそ充填ですね^_^;」
レジン修復を、このような言葉で表現する理由は何だろうか。
適当にやる(手抜き)前提の条件下で、どちらの治療時間が早いか、という議論は不毛でしかない。はっきりしているのは、論点をすり替えた、言いがかりに等しい指摘であることだ。
14
<指摘>
p75「抜髄した歯は、内部からの栄養供給がストップするので、乳白色だった歯が黒ずんでしまい、歯自体が脆くなって、歯の寿命は一気に短くなってしまう。
神経を抜かれた歯は「枯れ木」と一緒ですから長持ちしない。」
※抜髄しても歯の強度自体は変わらない。治療によって歯に薄い部分が出来てくることや、歯の感覚が鈍くなることで強すぎる力がかかりやすくなることで歯が割れやすくなるのではないかと考えられている。
https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00038649.html
<反証> 見解の相違 ④
抜髄した歯を「枯れ木」に例えることについて、田尾氏自身が上記URLのサイトにおいて、次のように発言しているので、指摘との矛盾を感じる。
『「枯れ木のようになる」という表現は正確ではないと思いますが、「折れやすくなっている」というイメージを伝えるのにはわかりやすい表現なのかな?と思います』(※田尾 耕太郎 回答日時:2011-09-22 03:48:18より抜粋)
神経を抜いた歯は、健全な生活歯よりも寿命は短い、ということは、エビデンスを議論する以前のコンセンサスだろう。
田尾 耕太郎氏が挙げている、抜髄した歯が割れやすい要因には同意できる。
ただし、「抜髄した歯の強度が、健康な歯と変わらない」という主張は、現時点でも歯科医によって意見が分かれている。田尾氏が主張の根拠として示す複数の論文は、あくまで傍証に過ぎず、それを集めたところで、推論の域を出ない。
現時点では、一人の患者の口腔内にある失活歯(抜髄した歯)と生活歯の強度を、条件を揃えて調べた研究論文は、見当たらないし、これから先も実施される可能性はゼロに等しい。なぜならそれは「人体実験」になるからだ。
15
<指摘>
p76「現在はマイクロスコープで拡大、可視化して根管治療を行うようになって、成功率は格段に上がりました」
※マイクロスコープの使用によって根管治療の成功率が格段に上がるというデータはない(使う必要が無いという意味ではない)。ただし、外科的歯内療法の成功率は高くなるというデータがある。
https://shikashiru.com/post/52.html
https://shikashiru.com/post/38.html
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑩
従来の「手探り」の根管治療に比べて、マイクロスコープを使用した根管治療の優位性については、議論の余地がない。これを証明する研究を実施するのは、倫理的にも難しいだろう。
全ての歯科治療が、エビデンスとなる研究論文に基づいているわけではない。
16
<指摘>
p78「根管にしっかり充填材が入っていないケースが実に多いというのだ。このような治療では、いずれ根管の先で炎症が起きて抜歯になる可能性が出てくる。」
※充填材が先まで入っているかどうかはあまり重要ではない。それよりも、根の中の細菌を十分に減らすことできているかどうか、外部からの細菌侵入を防ぐことが出来ているかどうかが重要。
<反証> 詭弁(もしくは捏造)というべき指摘 ⑪
上記の本書からの引用と、田尾氏の指摘をよく見比べていただきたい。
「充填材が先まで入っているか〜」という言葉は、本書にはないことが分かるはずだ。
「しっかり充填剤が入っていない」→「いずれ根管の先で炎症が起きて」という脈略を、勝手に「充填材が先まで入っているか〜」とすり替えている。
このような行為は「捏造」という言葉こそ相応しい。
さらに、根管治療の基本的な手順を定めた、歯内療法ガイドラインでは、次のように定めている。
「全ての根管を可能な限り根尖近くまで緊密に充填し、X線的に良好な根管充填をする。 過不足のある根管充填、レッジ形成、穿孔は避けるべきである」
「根尖」とは、根管の先端部分を指す。つまりガイドラインでは「根管の先近くまで緊密に充填」することを定めている。
根管内の消毒はもちろん重要だが、充填材は緊密にしっかり入れるのが、基本的な手技だ。
ガイドラインとは真逆と言える特殊な考え方を持ち出して、本書を間違いと決めつけるのは、詭弁でしかない。
17
<指摘>
p86「中高年世代に特有の虫歯として、「酸蝕症」と「根面う蝕」の2つがある。」
※酸蝕症は虫歯ではなく別の疾患。
<反証> 修正済みの指摘 ①
「酸蝕症」と「う蝕」は、いずれも酸によってエナメル質が溶ける病態である。ただし、「酸蝕症」は学問的にう蝕とは分けられている。したがって6月26日に修正を公表させていただいた。
18
<指摘>
p88「対策としては、早いうちに根面をレジンでカバーする方法が有効だ。」
※根面う蝕に対して、予防的に早いうちに根面をレジンでカバーするといったことは通常行われない。(根面は水分、有機質が多いため、レジンの接着力が落ちる)
https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00058601.html
<反証> 修正済みの指摘 ②
本書で「早いうちに」と記したのは、初期の根面う蝕を指しているのではなく、「疾患を放置せずに処置すべき」という主旨であった。そこで、ここは誤解が生じないように、「う蝕治療ガイドライン2版」に準拠して、次のような記述に修正する考えである。
→「根面う蝕の初期はフッ素による再石灰化、ある程度進行した修復処置にはレジン等でカバーする。」
19
<指摘>
p89「あなたの歯を守るための基礎知識」
「レジン修復」を歯医者に頼む。
※レジンは優れた材料であるが、テクニカルセンシティブであるため、十分な知識と技術を持った上で扱わないと予後が期待できない。レジンを勧めない歯科医師に無理にレジン治療を頼んでも、良い結果は期待できない。
<反証> 見解の相違 ⑤
「う蝕治療ガイドライン2版」において、レジンが適応となる虫歯であれば、レジン修復を推奨している。本来、う蝕治療を行う歯科医なら、レジン修復の技術をマスターしているのが当然だ。
「十分な知識と技術を持った上で扱わないと予後が期待できない」という設定自体が、不自然であり、田尾氏の指摘に妥当性は見いだせない。
20
<指摘>
p92~125 第三章「歯周病治療7つの罠」
※この章は全体的に良くまとまっており、患者への情報提供としても有益だと思う。
本書の内容に同意 ②
21
<指摘>
p95「ただし、この歯科医院の対応には、不可解な点が多い。「歯周病を歯槽膿漏と告げている」
※以前は歯周病は歯槽膿漏と呼ばれることが多かったため、年輩の方は歯槽膿漏と言われた方が理解されやすいケースが多い。歯周病も歯槽膿漏も呼び方が違うだけで同じものなので、患者さんに合わせて歯槽膿漏という用語を使っても特に問題はないと思われる。(歯周病の場合は歯肉炎も含み、歯槽膿漏はより進行した状態を表すといった差はあるが、臨床上そこまで厳密に用語の使い方にこだわる必要はないだろう)
<反証> 指摘自体が誤り ①
「歯周病も歯槽膿漏も呼び方が違うだけで同じもの」という主張は正確ではない。
歯周病は、炎症が歯肉に限局している「歯肉炎」、炎症が歯根膜、セメント質、歯槽骨など深部歯周組織に波及した「歯周炎」に大別されている。「歯槽膿漏」とは、重度の歯周炎で「膿」が出る状態を指すので、歯周病=歯槽膿漏ではない。
患者の誤解を避ける意味で、ここでは正確な診断名を告げるのが妥当だろう。歯周病治療の専門医であれば、「歯周病」を「歯槽膿漏」と患者には告げない。
22
<指摘>
p103「ミュータンス菌などは、酸素を必要とする「好気性菌」なので」
※ミュータンス菌は好気性菌ではなく、通性嫌気性菌。
<反証> 修正済みの指摘 ③
ミュータンス菌は、酸素があっても生存可能ではあるが、学問的には「通性嫌気性菌」に分類される。2版以降ではカットする修正を行った。
23
<指摘>
p128~174第四章「インプラントの光と闇」
※この章も全体的に良かった。患者への情報提供としても有益だと思う。
本書の内容に同意 ③
24
<指摘>
p176~203第五章「感染症リスク」
※この章も全体的には良いと思う。ただ、感染症対策は一見しただけでは患者さんにはまずわからないという問題がある。
H29年に厚労省から、保健所の立入検査の際に歯科医院の感染予防対策についても重点的にチェックするようにとの通知が出ているが、こうした第三者によるチェック体制を強化していかないことには改善は難しいのではないかと思う。
あと、指針はあくまでも「理想」なので、現実的に全ての医療機関がそれに添えるかどうかは疑問。「必要十分」という考え方もあり、なかなか難しい分野だと思う。
<反証> 指摘自体が誤り ②
感染予防に関する厚労省ガイドライン(指針)は、「理想」ではない。世界標準の感染予防であり、基本的に実施すべきものだ。
本書で示したとおり、海外では歯科治療による感染事故が発生している。患者は誰一人として、感染リスクのある歯科医院で治療など受けたくない。
オピニオンリーダーを自負する田尾氏でさえ、このような認識を公然と口にするのが、日本の歯科業界の実態だ。

25
<指摘>
p203「滅菌パックから器具を出す歯科医院は安心。」
※これは間違い。パックに入っていても滅菌が出来ていないケースは多い。
<反証> 見解の相違 ⑥
「滅菌パック」は、複数あるチェックポイントの一つの目安。ただし、これを信用できないなら、患者は歯科医院の滅菌作業をすべて確認しなければならない。
「パックに入っていても滅菌出来ていないケースは多い」と田尾氏は主張しているが、推測だけで無用な不安を煽るべきではない。

26
<指摘>
p203「HPで感染対策を公開している医院を選ぶ。」
※HPに書かれているからといって実際にやっているとは限らない。(何も書いていないよりは期待できるかも?という程度)
<反証> 見解の相違 ⑦
田尾氏は、歯科医院のHP制作を請け負う会社を経営しているので、実体験に基づく言葉なのだろう。HPの内容は信用しないほうがいい、という貴重なアドバイスに感謝したい。
但し、私が取材した歯科医院で、HPで感染予防を明示しながら、実施していないケースはなかった。
27
<指摘>
p203「クラスBタイプが安心。」
※クラスBタイプの滅菌機を導入している歯科医院は2~3%程度(GC社調べ)。クラスBによる感染予防上のメリットと、歯科医院選択の幅が狭まることのデメリットを考える必要がある。(個人的にはクラスBにこだわって歯科医院を選ぶといったことはお勧めしない)
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑫
本書では、クラスBだけでなく、クラスSの一部、ハンドピース専用滅菌器などを使用しているケースも紹介している。クラスBだけを取り上げているかのように言葉を抜粋するのは、フェアではない。

28
<指摘>
p206~225 第六章「モラルの崩壊」
※この章はネットの口コミや予約サイト、セラミック矯正などの問題について書かれているが、内容は良くまとまっており、患者さんへの情報提供として有益だと思う。
本書の内容に同意 ④
29
<指摘>
p228~249 第七章「高齢者に予防歯科は必要か?」
※予防歯科そのものについてはほとんど書かれていない。予防歯科を謳った営利目的の歯科医院に関する話が中心。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑬
7章のタイトルは「高齢者」ではなく「中高年に予防歯科は必要か?」。
この章では、4ページにわたって、カリスマ歯科医が確立した「予防歯科」について説明している。その他のページでも、予防歯科を掲げる歯科医院を受診する際の注意点を紹介しているので、「予防歯科についてほとんど書かれていない」は、妥当とは言えない。
30
<主張>
p231「”世界に名だたる日本の保険制度”と言われていますけど、現実は”早い、安い、どこでも、誰でも”という、質が低い歯科治療になっています。」
※全く同意できない。「質が低い」の根拠は何なのか?日本の歯科医療費は世界的に見て非常に安く、アクセシビリティにも優れている。歯科疾患実態調査のデータを見ても国民の口腔内の状態は年々良くなっており、(歯科医療費は安いにも関わらず) 現在では歯科先進国と言われる国と大差はない。
<反証> 見解の相違 ⑧
田尾氏が批判しているのは、予防歯科のカリスマと呼ばれる歯科医のコメントであるが、多様な意見があっていいと私は考えている。口腔内の原因除去をせず、応急処置的な虫歯治療を繰り返してきた日本の保険診療について、カリスマ歯科医なりの表現をしているだけだ。
ただし、「治療の質」は、保険と自費の違いよりも、歯科医の診療姿勢が大きく影響していることを、本書では示している。
31
<主張>
p236「自費のセールストークに時間をかけるくらいなら、しっかり患者の口腔内をクリーニングすべきだろう。」
※クリーニングに予防効果はない。(PMTCにも)
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑭
「クリーニングに予防効果がある」という主旨の記述は本書にないので、田尾氏の指摘は意図不明だし、牽強付会の感が否めない。
そもそも一般的な「予防歯科」とは、患者自身のセルフケアを中心に置き、定期的に歯科医院でケアと指導を受ける包括的なシステムである。歯科医院でのケアメニューに「PMTC=プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング」があり、これを患者には「クリーニング」と説明する場合は多い。
32
<指摘>
p241「この治療法は基本的に自費治療なので、歯科医院によって費用は異なる。」
※破折歯の接着修復に関する記事であるが、費用はインプラントと同じかそれ以上にかかることが多く(数十万円)、成功率はインプラントよりも低いという点に関しても言及して欲しかった。(接着修復にはこうした問題点があり、さらに技術・設備投資も必要となるため、行っている歯科医院が少ないということについても)
<反証> 見解の相違 ⑨
このパートでは、歯根破折が原因で抜歯する場合、「入れ歯」「ブリッジ」「インプラント」という3つの選択肢があると示している。
田尾氏がなぜ、最も費用が高いインプラントのみを提示するのか、理解に苦しむ。
ここでの主要テーマは、「抜歯」する前に、検討すべき治療法を提示することだ。
歯根破折の初期であれば「接着療法」によって歯を保存できる場合もある。眞坂信夫先生のグループや大阪大学、北海道大学によって、治療法として確立されている。
33
<指摘>
p243「失敗しない歯医者選びのポイント」
※口コミ&歯科サイト、ムック本、テレビCMに登場する歯科医院は避ける、「抜歯と診断」されたら、必ずセカンドオピニオンを受ける、など、7つのポイントが紹介されているが、うーん…といったところ。歯科医選びのポイントについては自分もまとめたことがあるので、よろしければ参考に。(個人的には自分がまとめたやつの方がいいなぁと思います。当たり前か^_^;)
https://www.ha-channel-88.com/tokusyuu/4.html
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑮
この部分については具体的な指摘はなく、自社サイトの宣伝を紛れ込ませている。
書評に便乗するのは、明らかに不適切な行為。
34
<指摘>
p245「虫歯治療は、可能な限りコンポジット・レジン修復で、歯を削る量を極力抑える方が長持ちする。レジン修復を嫌がる歯医者だったら、転院も考える。」
※レジンは良い材料であるがケースバイケース。レジン修復を嫌がるから転院というのは極論すぎる。
<反証> 詭弁というべき指摘 ⑯
このパートは、歯科医に治療方針をすべて任せるのではなく、患者自身が考えることを提案するものであり、世界的な「MI(ミニマルインターベンション)」の流れを具現化する虫歯治療として、レジン修復を紹介している。
全てレジン修復で治療すべきとは書いていないのに、田尾氏による「レジン修復を嫌がるから転院」という要約は、曲解でしかない。
一般的な読者なら、本文を次のように理解するのが自然である。
「可能な限り〜」→「状態によって、適応にならない場合もある」
「転院も考える」→「治療を継続するか、否かを検討する」

総評
全体的に、よく調べられていると思う。
特に、歯科界の構造的な問題や、トラブルに関しては、非常によくまとまっている。
一方で、医学的な内容、治療に関しては、内容の誤りや偏りが目立つ。歯科界が抱えている問題点については非常によくまとまっているだけに、惜しい。
医学的な内容に誤りがあると、読者が誤解し、適切な医療を受けられなくなってしまう恐れがある。専門家による事前チェックにより力を入れて頂くか、できればご自身で文献を読んで客観的に評価するスキルを身に付けて頂きたい。
そこさえ改善されれば、歯科業界についてここまで詳しいジャーナリストの方はなかなかいらっしゃらないと思うので、より社会、国民にとって有益な情報発信をして頂けるのではないかと思う。
田尾氏の「総評」に対して
34項目の主張を検討してみると、ガイドラインや引用論文と整合性が取れない主張が目についた。また、一般的な知見とは異なる、独自理論の主張を述べて、本書を「間違い」と決めつける姿勢には疑問に感じる。
田尾氏は、歯科医を相手にしたHP制作やSEO対策などの事業を行なっているので、本書が批判している歯科業界とは、利益相反がある。そのような立場を明かさず、レビューを投稿するのは、フェアではない。
文責:岩澤倫彦